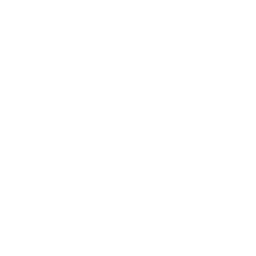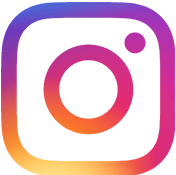ブログ
ブログ
テニスをしている成長期に多い足の痛み ~シーバー病と当院での治療について~
- 2025/10/17
- 足の痛み
こんにちは!





今回はテニスをしている
成長期に多いスポーツ障害について
書いていきたいと思います!
成長期の骨の特徴
成長期の骨格には骨端線(こったんせん)といった
成長期の子供の骨の両端にある
軟骨組織でできた成長の為の特別な層が存在します。
活発な骨形成が行われることで
骨の長さの成長が行われています。
骨端線は成長軟骨組織であるため
力学的負荷が加わった時にストロングポイントとなり
特有の損傷を起こします。
急性の怪我ではなく
繰り返す負荷によっておこる
慢性障害として骨端線に生じた損傷を
骨端症といいます。
成長期には骨の長さの活発な成長の結果
筋肉の成長が骨の成長に比べ間に合わないため
筋肉の短縮によって
筋肉の柔軟性低下が起こってしまいます。
柔軟性の低下は体の動きが硬くなるだけでなく
骨端症のリスクをアップしてしまいます。
身長増加がもっとも大きい年齢は
13歳であり、その時期以降にもっとも硬い時期があります。
筋肉の増加や骨量の増加が最も大きい時期は
13歳により1年遅いとされています。
その為中学生では骨密度はそんなに高くなく
成長の遅い子どもでは高校生になっても
十分な骨密度にたっしていないと予想がされます。
高校生だからと負荷を強くした場合
骨端症などを起こすリスクがあるため注意が必要です。
骨端症の代表例
・上腕骨近位骨端線離開
・野球肘
・オスグット病
・シーバー病
などがあげられます。
その中でも今回はテニスに多い
シーバー病について書いていきたいと思います。
シーバー病とは?
シーバー病は成長期におこる
踵の骨端症になります。
骨端線の閉鎖前に踵骨隆起の骨端が炎症を起こし
踵に痛みを起こします。
オスグット病と同程度かそれ以上に多い
骨端症ですが認識しないまま症状が
消失することが多い疾患です。
小学生中学年頃に多く発生し
中学生になるころには痛みが消えてることが多いのが特徴です。
なぜテニスに多く発症するのか?
テニスはコートを素早く走り回る競技の為
急激な方向転換やストップ、ダッシュなど
着地時や踏み込み時に踵に
強い衝撃が加わることから発症しやすいとされています。
シーバー病の痛みとして
ランニングの着地や蹴りだしの際に
アキレス腱の付着部を介した
下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)の引っ張りを受けて痛みを出しますが
足底腱膜の引っ張りも加わり圧迫の負荷も
加わり痛みを起こします。
特にサッカーや野球などのジャンプや長時間走り続けるスポーツ
裸足で行う剣道や武道、体操などを熱心にしている子どもにも多くみられます。
画像の炎症の部分に痛みを起こしやすくなります。
主な症状
・かかとを押した時の痛み(圧痛)
・かかとの軽い腫れ
・歩行時の痛み
・痛みからつま先あるきをしている
などがあります。
痛みは激しい運動後に起こることが多く
片足のみや両足に痛みが起こることがあります。
シーバー病のケア方法
かかとの痛みを起こした時は安静にしかかとへの負担を軽減し炎症を抑えることが重要になります。
痛みがある場合は運動を避けることがいいです。
また運動後などはアイシングで患部の炎症と痛みを抑えることが大切になります。
アイシングはかかとに氷嚢や保冷剤で15~20分程度あて冷やします。
これにより炎症を抑えることが大切になります。
また日ごろからのストレッチも大切になります。
原因となるふくらはぎのストレッチや
足裏のマッサージなどを行うことで硬さを取っていくことが重要になります。
足裏にはテニスボールを転がしたり
指を使うようにしっかり動かすことが大切になります。
予防ではかかとに衝撃が加わるのを抑えるために
クッション性の高い靴を選ぶようにしましょう。
底が薄い靴だと衝撃が加わりやすく
痛みを起こしやすくなります。
またインソールの使用も大切になっていきます。
クッション性のあるインソールや
ヒールカップ(かかとを安定させる装具)を使うと
かかとへの負担が軽減され痛みを軽減することがあります。
当院での治療
当院では痛みの原因にアプローチし
痛みや動きを改善します。
炎症や痛みに特殊な治療器を使い
痛みや炎症を取っていきます。
筋肉が原因の場合鍼を使い悪さをしている筋肉に
直接アプローチします。
当院ではオーダーインソールを取り扱っているため
運動中や普段での生活でのサポートもできます。
当院はジム併設なため痛みの出ないための
トレーニングやストレッチも指導できます。
成長期のかかとのいたみ
成長期の体の痛み
成人でのかかとの痛みなど
気になりましたらひどくなる前に早めにご相談ください。
大阪市東住吉区にあるスポーツ専門治療院
針中野フィジカルケア鍼灸整骨院
スポーツされていない方も多数来院されていますのでお気軽にご相談ください。
電話お問い合わせ・ホームページ
メールお問い合わせ

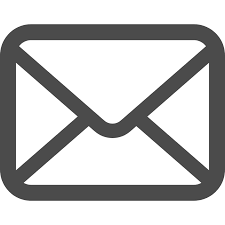

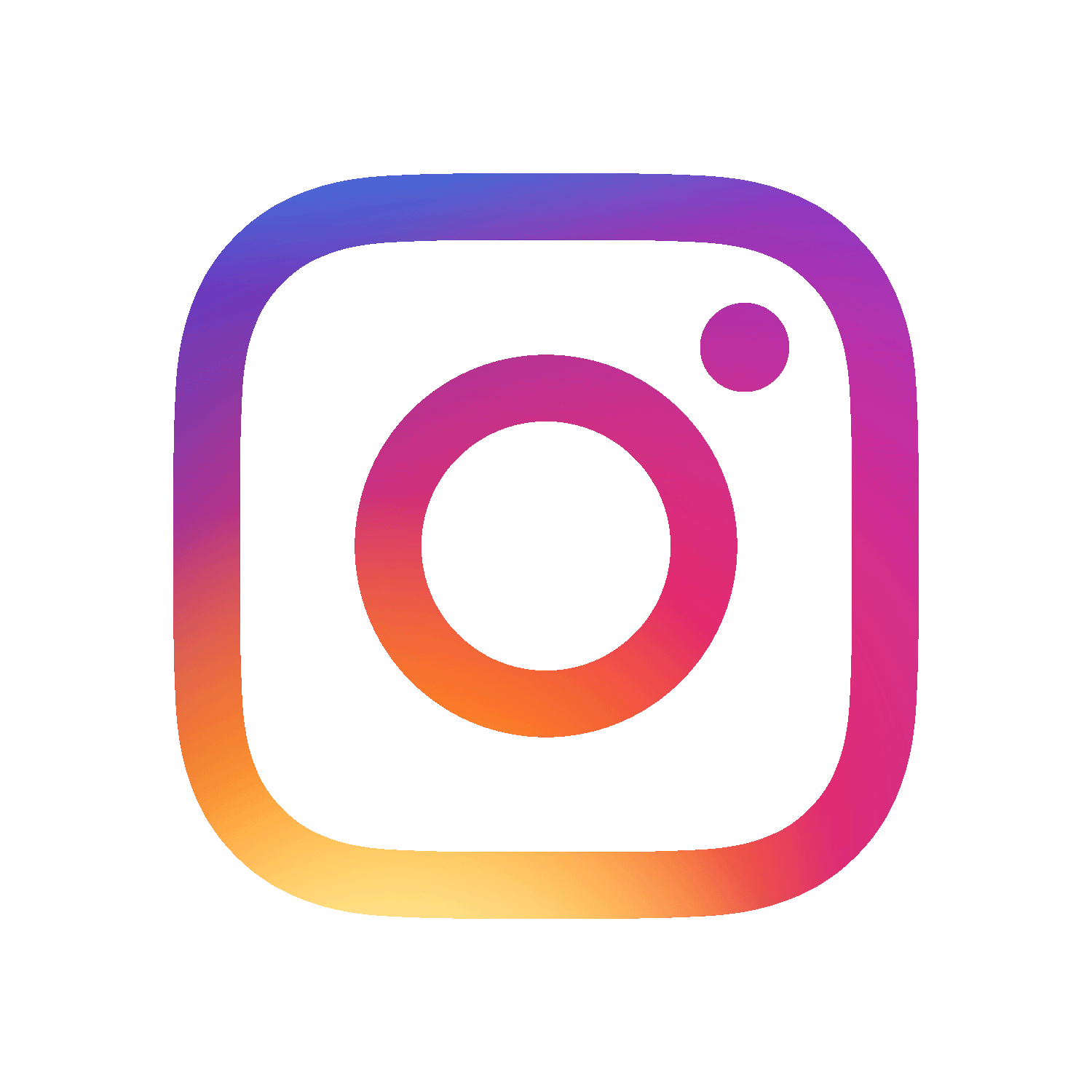

 HOME
HOME 当院のご案内
当院のご案内 診療案内
診療案内 営業日
営業日 料金のご案内
料金のご案内 新着情報
新着情報 患者様の声
患者様の声 Q&A
Q&A 求人情報
求人情報