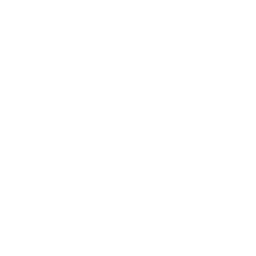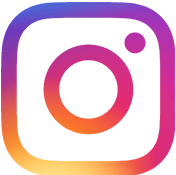ブログ
ブログ
格闘技やラケット競技で多い手首の痛み ~原因と改善方法について~
- 2025/08/04
- 手の痛み
こんにちは!


 転倒して手をついた時や手首を捻る動作が多いスポーツ(野球、ゴルフ、テニス)などに損傷しやすいです。
転倒して手をついた時や手首を捻る動作が多いスポーツ(野球、ゴルフ、テニス)などに損傷しやすいです。




格闘技やラケット競技に多い手首の痛みについて書いていきます!
足首の捻挫はよく耳にするかと思いますが手首にも捻挫は存在するんです。
手首の痛みで悩んでいる人は多くいます。
例えば手首を使うスポーツの人、仕事柄よく使う人、主婦の方などに多いです。
手首の捻挫とはどんな状態?
手首捻挫とは手首の関節を支える靭帯が損傷した状態になります。
転倒して手をついたり、スポーツなどで手首を強くひねった際に起こります。
格闘技ではパンチの際に手首に大きな力が加わり捻挫をしやすくなります。特に手首を固定せず打つと起こりやすくなります。
また攻撃を受け止める際や転倒時に手をついてしまうことで捻挫を起こすことがあげられます。
特に初心者は手首の使い方がわからなく力のコントロールも難しいため捻挫をしやすい傾向にあります。
ラッケト競技ではバドミントン、テニス、卓球などラケットを振る動作を繰り返すことで手首の関節や靭帯に負担をかけやすくなります。
またボールを打つ衝撃で手首に負担をかけ捻挫しやすくなります。

手首の捻挫をしたときの症状として
手首周辺や関節に痛みを伴います。特に動かした時の痛みが強くなります。痛みから手首の可動域が狭くなることがあります。
また腫れが起こり怪我した部分に熱を持つことがあります。
捻挫は3つの程度に分け重症度を判断できます。
1.軽度捻挫(Ⅰ度)
靭帯が少し伸びた状態
痛みは軽度で、腫れや皮下出血も少ないです。
2.中等度捻挫(Ⅱ度)
靭帯の一部が断裂した状態
痛みや腫れが強く、関節の動きも制限されることがあります。
3.重度捻挫(Ⅲ度)
靭帯が完全断裂。
関節の不安定性が強く、強い痛みと腫れを伴います。
捻挫は靭帯だけでなく、他の組織(関節包、腱)なども損傷している場合があるので注意が必要です。
手首捻挫では手首の何が損傷する?
手首、手のひら、指にはたくさんの靭帯があり手の骨を連結させています。
その中でも特に手首捻挫で損傷する可能性のある靭帯はTFCC(三角線維軟骨複合体)や、橈骨手根靭帯、尺骨手根靭帯になります。
TFCC(三角線維軟骨複合体)とは手首の小指側にある靭帯と軟骨の複合体で、手首の安定性に重要な役割をしています。
 転倒して手をついた時や手首を捻る動作が多いスポーツ(野球、ゴルフ、テニス)などに損傷しやすいです。
転倒して手をついた時や手首を捻る動作が多いスポーツ(野球、ゴルフ、テニス)などに損傷しやすいです。
橈骨手根靭帯とは親指側の手首の靭帯で、手首の動きをサポートしている靭帯です。
尺骨手根靭帯とは小指側にある手首の靭帯で、TFCCと合わせて手首の安定性に重要になります。

手首捻挫の予防として格闘技の場合
正しいフォームを習得し、パンチを打つ際には手首を固定し正しいフォームで打つことが大切になります。
また投げのある競技では受け身をしっかりと習得することが大切です。倒れた時に手をついた場合手首の捻挫だけでなく肘の骨折も考えられるため受け身をしっかりと習得しましょう。
ラケット競技の場合
無理な力でラッケトを振ったり、ボールを強く打ったりすることは避け、適切な負荷でプレーすることが大切になります。
また、手首を保護するためのバンテージやテーピングを使用することも重要になります。
特に捻挫の経験がある人は再発防止のため着用をお勧めします。
手首の捻挫を防ぐためストレッチや筋力トレーニングを行うことも大切になります。
手首の柔軟性を高めるため運動前や運動後のストレッチが大切になります。

このような前後左右しっかり伸ばすことが大切になります。
トレーニングでは手首を鍛えるようにしていきます。
グーパー運動
手をグーとパーに開閉する運動出、手首だけでなく握力も鍛えられます。
リフトカール
ダンベルやバーベルを使い、手のひらを上に向け手首を曲げ伸ばしするトレーニングです。手首の屈曲を鍛えます。
リバースリフトカール
リフトカールの反対の運動になります。手首の伸展を鍛えます。
またハンドグリップやパワーボールを使うのも手首のトレーニングになります。
当院での治療
当院では様々な競技の方がご来院相手くださるため手首や足首捻挫の治療を得意としています。
当院ではまず痛めている原因を見つけアプローチしていきます。
痛めている原因となっているものを取ります。
捻挫により腫れや痛みがひどい場合には特殊な治療器を使い腫れや痛みを抑えます。
筋肉の動きが悪い場合鍼治療を行い筋肉に直接アプローチし動きを良くしていきます。
当院ではジム併設の為必要なリハビリ、トレーニングを提案します。
必要な方にはテーピングを使用し動きを助けます。
手首の痛みや違和感、捻挫した方などはお気軽にご相談、ご来院ください。
大阪市東住吉区にあるスポーツ専門治療院
針中野フィジカルケア鍼灸整骨院
スポーツされていない方も多数来院されていますのでお気軽にご相談ください。
電話お問い合わせ・ホームページ
メールお問い合わせ

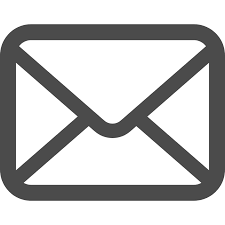

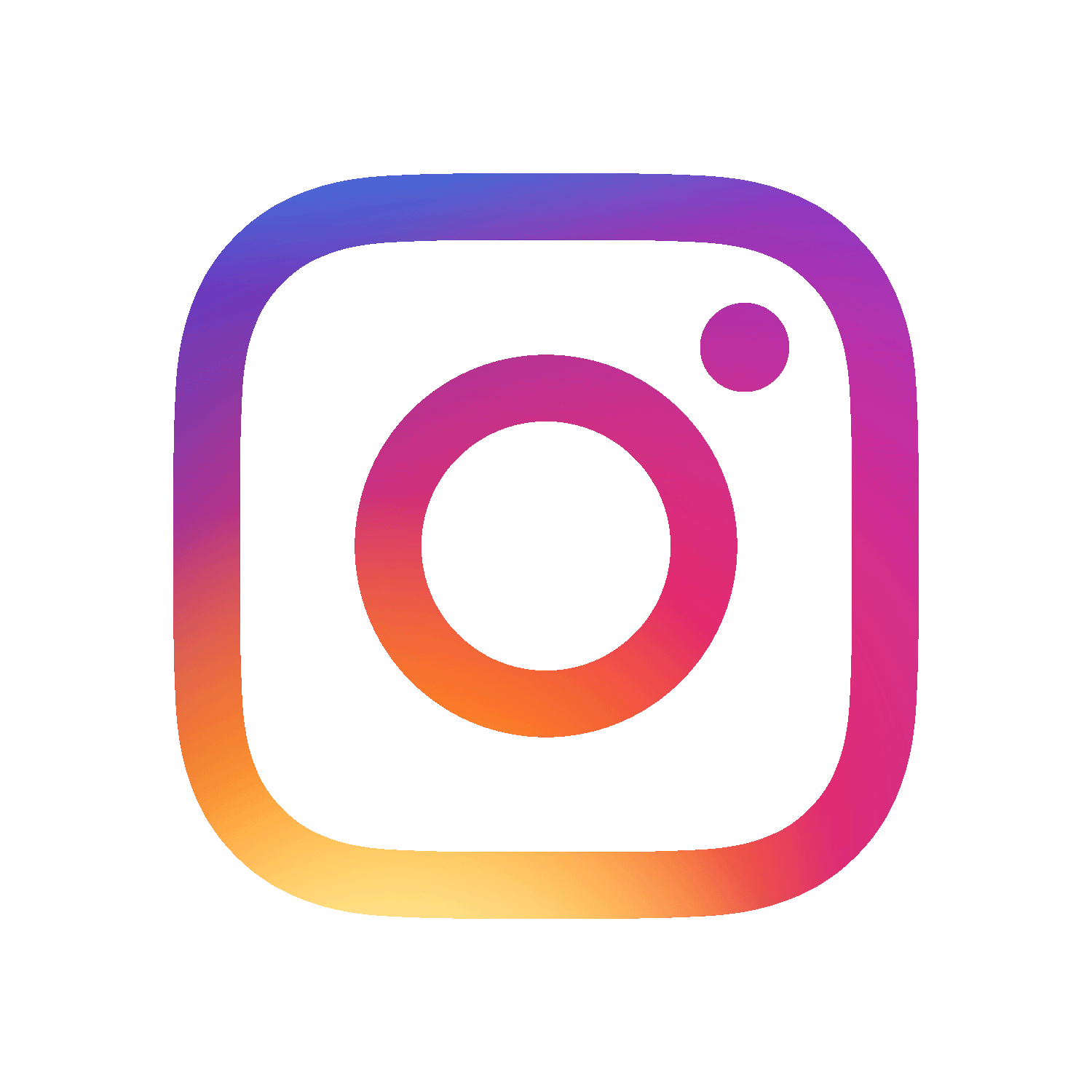

 HOME
HOME 当院のご案内
当院のご案内 診療案内
診療案内 営業日
営業日 料金のご案内
料金のご案内 新着情報
新着情報 患者様の声
患者様の声 Q&A
Q&A 求人情報
求人情報